| 会報 北方博物館交流 総目次 | ||
| 第25号 | 2013,3 特集 カムチャツカ考古学の最前線 | |
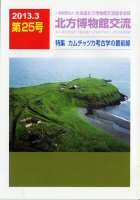 |
表紙写真解説 カムチャツカ半島西岸ジユバノヴオ遺跡 | 野村 崇 |
| 巻頭言 北に向った和人の姿を追う | 関根 達人 | |
| 事業報告 二〇一二年度の事業報告と新年度計画 | 柏倉 勝雄 | |
| カムチヤッカ半島北部カラガ湾周辺の遺跡を訪ねて | 高瀬 克範 | |
| カムチャツカ考古学の最前線 A・V・プタシンスキー | 高瀬克範訳 | |
| カムチャツカ半島のイテリメンの漁撈文化について | 杉浦 重信 | |
| 「十五歳露国少年の書いたカムチャツカ旅行記」とアルセーニエフ | 野村 崇 | |
| 廣瀬神社を訪ねて | 舟山 廣治 | |
| 拓聖 依田勉三を訪ねる十勝への旅 | 五百木康司 | |
| 北海道北方博物館交流協会の刊行物一覧 | 編 集 部 | |
| 事務局だより・編集後記 | ||
| 紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第23・24号 | 2012,3 | |
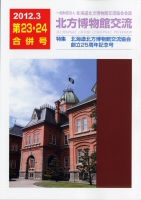 |
巻頭言 東日本大震災に人間の歴史を想う | 松本 建速 |
| 事業報告 二〇一〇・一一年の事業報告と新年度の計画 専務理事 | 柏倉 勝雄 | |
| 北海道北方博物館交流協会設立25周年記念講演会 | 岡田和也 カーチヤ |
|
| 「追憶のロシヤ~ハバーロフスク叙景1989-2011~」講演録 | ||
| オランダ博物館の旅 | 野村 崇 | |
| モンゴル高原に旧石器遺跡を探る | 高倉 純 | |
| 北サハリン博物館交流の旅(Ⅲ) ティモフスコエからアレキサンドロフスク・サハリンスキーを巡る | 遠藤 籠畝 | |
| 富良野出土のイノシシと須恵器の趨について | 杉浦 重信 | |
| 『北海道北方博物館交流協会二五年史』の刊行 | 亀谷 隆 | |
| 樺太庁農事試験場開設初期の試験調査(付 樺太庁農事試験場年表) | 舟山 廣治 | |
| 事務局だより・編集後記 | ||
| 紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第22号 | 2010,11 | |
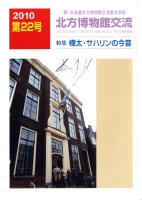 |
表紙解説 シーボルトハウス | 野村 崇 |
| 巻頭言 北大で開かれたマキシモヴィツチ展示 | 高橋 英樹 | |
| 事業報告 二〇〇九年度の事業と新年度の計画 | 柏倉 勝雄 | |
| 二十五年の足跡としての平成二十一年度事業 | 亀谷 隆 | |
| サハリンにおける「日本時代」陶磁器の考古学的調査経過報告 | 野村 崇 卜部信臣 遠藤龍畝 関川修司 |
|
| サハリン州ポロナイスク出土の「日本時代」陶磁器に関する調査 | 野村 崇 | |
| サハリン博物館交流の旅(Ⅱ) | 遠藤 龍畝 | |
| サハリン ポロナイスク(旧敷香)の旅 | 卜部 信臣 | |
| 露国植物学者 マキシモヴィツチと日本の植物補遺(続) | 舟山 廣治 | |
| オロツコ族に就いて 鳥 居 籠 蔵 | 杉浦重信補注 | |
| 樺太における図書館設置運動 | 鈴木 仁 | |
| 事務局だより・編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第21号 | 2009,3 | |
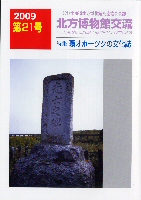 |
・表紙写真 北千島シュムシュ島の「志士之碑」 | 野村 崇 |
| ・巻頭言 境界-それを超える沖合自由航行権- | 天野 哲也 | |
| ・二○○八年度の事業と新年度の計画 | 柏倉 勝雄 | |
| ・『北海道・四季の美』-栗谷川健一と袴田睦美の芸術- | 亀谷 隆 | |
| ・アムール川河口域の考古学と日本列島北辺域の先史文化 | 福田 正宏 | |
| ・カムチャツカ半島出土土器の年代をさぐる | 高瀬 克範 | |
| ・カムチャツカ紀行 | 中山 英司 | |
| 杉浦 重信 校註 | ||
| ・厚真町上野地区発見の丸木舟と松浦武四郎の厚真行 | 蓑島 栄紀 | |
| ・メキシコの遺跡とメキシコ国立人類学博物館 | 野村 崇 | |
| ・樺太における農作物の病害 | 舟山 廣治 | |
| ・事務局だより・編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第20号 | 2008,3 | |
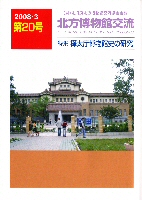 |
・表紙関連写真 樺太庁博物館の今昔 | |
| ・巻頭言 南サハリンの日本期の歴史的建造物調査 | 角 幸博 | |
| ・二〇〇七年度の事業と新年度の計画 | 柏倉勝雄 | |
| ・『北海道・四季の美』展開催交渉・調査派遣団記 | 舟山廣治 柏倉勝雄 亀谷 隆 |
|
| ◎特集 樺太庁博物館史の研究 | ||
| 樺太庁博物館概史 | ||
| 樺太庁博物館の規定・規則 | 舟山廣治 | |
| 樺太庁博物館職員の配置体制 | 舟山廣治 | |
| 樺太庁博物館の出版物とシリーズ 『樺太叢書』・『樺太庁博物館叢書』 | 出村文理 野村 崇 |
|
| 樺太庁博物館刊行の『博物館教育』と教育普及活動 | 野村 崇 | |
| 樺太庁博物館のジオラマとその製作者 | 宮本劭 | |
| 建築物・樺太庁博物館 | 関川修司 | |
| 樺太庁博物館人物伝 | ||
| ①初代事務主筆 栃内壬五郎 | 舟山廣治 | |
| ②初代専任主事 菅原繁蔵 | 舟山廣治 | |
| ③鳥類研究者 高橋多蔵 | 舟山廣治 | |
| ④考古資料収集者 木村信六 | 野村 崇 | |
| ⑤技術員としての 考古学者 奥山鍠吉 | 野村 崇 | |
| ⑥樺太庁博物館の人びと | 鈴木 仁 | |
| 樺太庁博物館年表 | ||
| 亀谷 隆 | ||
| 第19号 | 2007,3 | |
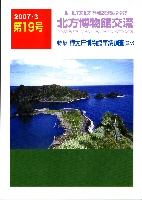 |
◎特集 旧樺太庁博物館事績調査(続々) | |
| ・表紙解説 モネロン島の今昔 | 野村 崇 | |
| ・巻頭言 樺太に育って | 神沢 利子 | |
| ・二〇〇六年度の事業と新年度の計画 | 柏倉 勝雄 | |
| ・樺太庁博物館刊行の出版物とシリーズ『樺太叢書』・『樺太庁博物館叢書』 | 野村 崇 出村 文理 |
|
| ・樺太庁博物館に関する調査 (続々) | 舟山 廣治 | |
| ・千島列島にオホーツク文化の北限を求めて | 天野 哲也 | |
| B・フィッツヒユー・Ⅴ・シユーピン | ||
| ・カラーページ | ||
| ・サハリン州郷土博物館での二つの出会い | 宮本 劭吉 | |
| ・樺太アイヌの人たちの追憶 | 卜部 信臣 | |
| ・サハリン博物館交流の旅 | 遠藤 龍畝 | |
| ・華中の遺跡と博物館を訪ねて | 倉橋 直孝 | |
| ・デルス・ウザーラ絵物語展 | 亀谷 隆 | |
| ・アンデス遺跡紀行 | 野村 崇 | |
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第18号 | 2006,3 | |
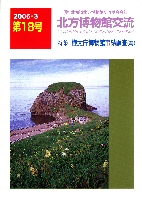 |
◎特集 旧樺太庁博物館事績調査(続) | |
| ・表統解説 サハリン西海岸の秘境 クルグリ岬と遺跡群 | 野村 崇 | |
| ・巻頭言 フゴッペ洞窟壁画の原郷土 | 小林 達雄 | |
| ・二00五年度の事業と新年度の計画 | 柏倉 勝雄 | |
| ・樺太庁博物館に関する調査(続) | 舟山 廣治 | |
| ・樺太庁博物館とサハリン州郷土博物館 | 笹倉いる美 | |
| ・博物館交流団に参加して | 山口 真 | |
| ・カナダ アルバータ南西部の歴史サイトと博物館 | 北川 芳男 | |
| ・サハリン西海岸クルグリ岬遺跡群踏査記 | 野村 崇 | |
| ・カラーページ | ||
| ・カムチャツカ半島ナルィチェヴォ遺跡群を訪ねて | 高瀬 克範 | |
| ・サハリンに土屋根住居を探して | 高田 和徳 | |
| ・私のふるさと、カザフスタン | サリモヴア・グリナラ | |
| ・樺太庁博物館に関する新資料 | 鈴木 仁 | |
| ・事務局だより・編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第17号 | 2005,3 | |
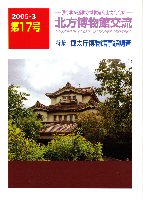 |
◎特集 「旧樺太庁博物館事績調査」 | |
| ・表統解説 樺太庁博物館の建物 | 関 川 修 司 | |
| ・巻頭言 | ||
| テルスの還る森 | 津曲 敏郎 | |
| ・二〇〇四年度の事業と新年度の計画 | 柏倉 勝雄 | |
| ・ユジノサハリンスク再訪 -北方文化の定義を考える- | 岡田 淳子 | |
| ・旧樺太廳博物館の事績に関する調査 | 舟山 廣治 | |
| ・サハリン州郷土博物館の建物に感激 | 関川 修司 | |
| ・樺太関係資料館について | 鈴木 仁 | |
| ・サハリン州郷土博物館はいま!(講演録) タチアナ・ローン | ||
| ・カラーページ | ||
| ・ウスチ・アインスカヤ遺跡紀行 | 野村 崇 | |
| ・デスモスチルスの発掘物語 | 北川 芳男 | |
| ・鳥居龍蔵の南樺太調査について | 杉浦 重信 | |
| ・黒澤明監督作品『デルス・ウザーラ』制作の現場(講演録) | 野上 昭代 | |
| ・事務局だより・編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 表紙撮影 | 野村 崇 | |
| 第16号 | 2004.3 | |
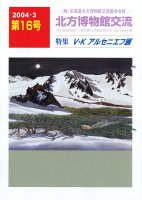 |
◎特集 「∨・Kアルセニエフ展」 | |
| 表紙解説 Ⅴ・Kアルセニエフとデルス・ウザーラ沿海州探検絵物語(続) | 舟山 廣治 | |
| ・巻頭言 ロシア極東の博物館 | 荒井 信雄 | |
| ・二〇〇三年度の事業と今後の計画 | 柏倉 勝雄 | |
| ・特別展示「V・Kアルセニエのロシア沿海州探検とデルス・ウザーラ」終了報告 | 矢島 睿 | |
| ・講演会一、十九世紀後半~二十世紀初頭の沿海州 エレナ・ヴラジミロヴナ・スウシコ | ||
| 講演会二、アルセニエフの沿海州探検とデルス・ウザーラ オリガ・ヴィクトロヴナ・マズニヤク | ||
| ・北海道開拓とピアソン記念館 | 伊藤 悟 | |
| ・カムチャツカ小紀行 | 菊池 徹夫 | |
| ・カラーページ | ||
| ・ニブヒのサケ解体作業 | 高田 和徳 | |
| ・カムチャツカ半島中央部の獣皮加工 | 高瀬 克範 | |
| ・旧樺太廉博物館と樺太植物の研究 | 舟山 廣治 | |
| ・ジュパノヴォ遺跡を訪ねて | 野村 崇 | |
| 事務局だより・編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第15号 | 2003.3 | |
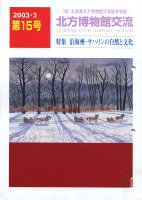 |
◎特集 沿海州・サハリンの自然と文化 | |
| ・表紙解説 Ⅴ・K・アルセニエフとデルス・ウザーラ沿海州探検絵物語 | 舟山 廣治 | |
| ・巻頭言 デルス・ウザーラのルートを辿って | 辻井 達一 | |
| ・二〇〇二年度の交流事業と今後の計画 | 柏倉 勝雄 | |
| ・アルセニエフ展開催に向けて | 舟山 廣治 | |
| ・特別展 Ⅴ・K・アルセニエフーロシア沿海州探検とデルス・ウザーラー概要 | ||
| ・ロシア極東の冒険家Ⅴ・Kアルセニエフを日本に紹介した人たち | 矢 島 睿 | |
| ・国際貿易港敦賀の足跡 | 鈴木 仁 | |
| ・アイヌは環境とどのように関わってきたのか | ||
| -フィールドワークからみたアイヌのエコシステム・カムイ・ジエンダーー 瀬川 拓郎 | ||
| ・ロシア再び | 斉藤代志美 | |
| ・大地震に襲われた縄文の村 | 佐々木栄一 | |
| ・花 巡 礼 | 田中 稔 | |
| ・サハリン調査こぼればなし 植物と人びと | 水島 未記 | |
| ・南サハリン・アントノヴオ遺跡について | 杉浦 重信 | |
| ・南サハリン考古学紀行 | 野村 崇 | |
| ・事務局だより・編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第14号 | 2002.3 | |
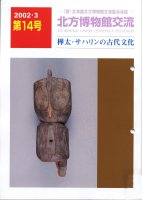 |
◎特集 樺太・サハリンの古代文化 | |
| ・巻頭言 | ||
| 東北大学考古学研究室によるサハリン南部先史遺跡の予備調査 | 須藤 隆 | |
| ・事業報告 | ||
| ・二OO二年度の交流事業と今後の計画 | 柏倉 勝雄 | |
| ・ウラジオストク訪問記 | 舟山 廣治 | |
| ・沿海州を訪ねて | 灰谷 慶三 | |
| ・大形木製文化財の保存 | 岡田 淳子 | |
| ・ロシア訪問雑感 | 河田 嗣郎 | |
| ・アムール川のほとりに生きて | 斉藤代志美 | |
| ・講演会 近年のサハリンにおける考古学事情 M・M・プロコフィエフ | ||
| ・表紙写真解説 サハリンの木偶 | 小西 雅徳 | |
| ・カラーページ | ||
| ・南サハリンの小能登呂・馬群潭土城について | 杉浦 重信 | |
| ・アムール河口アエロボルトエ遺跡での発掘調査参加記 | 福田 正宏 | |
| ・事務局だより・編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第13号 | 2001.3-(財)北海道北方博物館交流協会会誌 | |
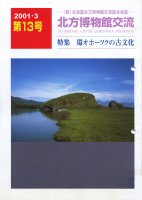 |
◎特集「環オホーツクの古文化」 | |
| ・ カムチャツカ半島バラトゥンカ川の遺跡 | 野村 崇 | |
| ・千鳥列島北部地域の考古資料 | 北構 保男 | |
| ・二〇〇〇年度の交流事業と今後の計画 | 相倉 勝雄 | |
| ・先住民博物館の新構想 | 岡田 淳子 | |
| ・丸木舟による宗谷海峡の横断(下) | 梅木 孝昭 | |
| ・露国植物学者マキシモヴィツチと日本の植物補遺 | 舟山 廣治 | |
| ・平成一二年度事業 北海道・ロシア文化交流事業講演会『極東ロシアの歴史と生活』 | ||
| ・アルセニエフ記念国立沿海地方博物館の歴史と文化資料 クリメンコ・イライダ・ニコラエヴェナ | ||
| ・ロシア・極東の歴史と人々の生活~Ⅴ・K・アルセニエフの生涯 ナム・イリナ・パヴロヴナ | ||
| ・ウラジオストク訪問記 | 北川 芳男 | |
| ・カラーページ | ||
| ・土鍋のきた道 | 野村 崇 | |
| ・カムチャツカ考古学の先駆者中山英司 | 杉浦 重信 | |
| ・間宮海峡における考古学調査紀行 | 福田 正宏 | |
| ・特別展「石田収蔵-謎の人類学者の生涯と板橋-」を終えて | 小西 雅徳 | |
| 事務局だより・編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第12号 | 2000.3 | |
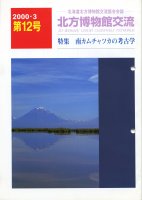 |
◎特集「南カムチャツカの考古学」 | |
| ・表紙写真にちなんで カムチャツカ半島の自然と遺跡 | 北沢 実 | |
| ・巻頭言 クラスキノ土城の発掘から 青山学院大学教授 田村 晃一 | ||
| ・一九九九年度の交流事業と今後の計画 | 柏倉 勝雄 | |
| ・マキシモヴィッチと日本の植物 | 舟山 広治 | |
| ・サハリン州の芸術文化活動事情 | 紺谷 憲夫 | |
| ・現代カムチャツカ先住民社会と経済活動 | 渡部 裕 | |
| ・丸木舟による宗谷海峡の横断(上) | 梅木 孝昭 | |
| ◎南カムチャツカにおけるアイヌ文化の考古学的研究 | ||
| ・一九九九年度カムチャツカ半島の考古学的調査概要 | 野村 崇 | |
| ・カムチャッカ半島南東部ジュパノヴォ遺跡出土の日本製品 野村 崇・杉浦 重信 | ||
| ・カラーページ | ||
| ・ジユパノヴォ遺跡出土の寛永通宝・石器・陶磁器・カムチャツカ各地の遺物・アヴァチャ湾岸の遺跡 | ||
| ・カムチャツカの先史時代 A・K・ポノマリェンコ | ||
| ・カムチャツカ半島アヴァチャ湾周辺の遺跡 | 杉浦 重信 | |
| ・事務局だより・編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第11号 | 1999.2 | |
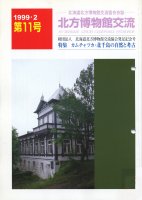 |
・表紙写真にちなんで カムチャツカ半島と郷土博物館 | 野村 崇 |
| ・巻頭言 ユーラシアの放浪者フィリップ・エフレモフ | 加藤 九祚 | |
| ・財団法人北海道北方博物館交流協会の発足に当たって | 舟山 廣治 | |
| ・一九九八年度の交流事業と今後の計画 | 柏倉 勝雄 | |
| ・カムチャツカ紀行-ゲーゼル渓谷への旅 | 北川 芳男 | |
| ・カムチャツカ・北千島考古の旅 | 野村 崇 | |
| ・カムチャツカ訪問記 | 杉浦 重信 | |
| ・カムチャツカを訪ねて | 土屋 隆幸 | |
| カラーページ | ||
| ・カムチャツカ郷土博物館訪問・カムチャツカの自然・占守島の自然と文化・サハリン絵画展 | ||
| ・サハリンの絵画展“開催に当たって | 舟山 廣治 | |
| ・サハリン美術展の顛末 | 中村 斎 | |
| ・Ⅴ・K・アルセーニュフの沿海州探検 | 矢島 睿 | |
| ・「北方ユーラシアの民族と文化をめぐつて」 カムチャツカ考古学のあゆみ | 杉浦 重信 | |
| 編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第10号 | 1997.12 | |
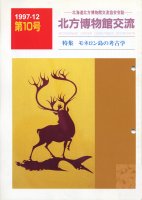 |
・会長渡邊左武郎先生の御逝去を悼む | 舟山 廣治 |
| ・巻頭言 サハリン島の先住民 そしてゾーヤさん | 大塚 和義 | |
| ・一九九七年度の交流事業と今後の計画 | 柏倉 勝雄 | |
| ・サハリン初めての旅から | 菊池 徹夫 | |
| ・モネロン島記 | 上野 武 | |
| ・モネロン島遺跡紀行 | 野村 崇 | |
| ・ウラジオストック紀行 | 舟山 廣治 | |
| ・特別講演会 | ||
| ・ロシア極東域との経済・文化交流の展望 大道寺 小三郎 | ||
| ・カラーページ | ||
| ・極北チュクチ半島における考古学的調査 セルゲイ・アルチュノフ | ||
| ・サハリンにおける松浦武四郎の記念碑建立と展示会のこと | 梅木 孝昭 | |
| ・博物館ノート 小規模博物館の国際化 | 北川 芳男 | |
| ・表紙解説 | 中村 斎 | |
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第9号 | 1996.12 | |
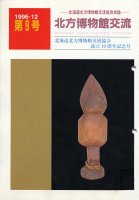 |
・表紙写真にちなんで 樺太の木偶 | 野村 崇 |
| ・巻頭言 初めてのヤクーツク旅行の思い出など | 宇田川 洋 | |
| ・一九九六年度の交流事業と今後の計画 常務理事 柏倉 勝雄 | ||
| ・アムール河口部の遺跡分布調査 | 臼杵 勲 | |
| ☆特集 北海道北方博物館交流協会設立十周年記念講演会 | ||
| ・北海道北方博物館交流協会十周年を迎えて 理事長 舟山 廣治 | ||
| ・国立芸術・歴史・建築保存博物館コレメンスコエ リリアナ・ドンスキー | ||
| ・国立文学博物館事情 イリーナ・シヤハロワ | ||
| ・カラーページ | ||
| ・北海道北方博物館十周年記念講演会 レセプション アムール河岩絵紀行 アムール河口の遺跡と博物館 コスケール洞窟とショウベ洞窟の岩面画 |
||
| ・講演会 コスケール洞窟とショウベ洞窟の岩面画 | 小川 勝 | |
| ・ポロナイスク地方における初期考古学的遺物 Ⅴ・D・フエュドルチュク | ||
| ・アムール河岩絵紀行 | 野村 崇 | |
| ・石田収蔵と樺太の調査 | 小西 雅徳 | |
| ・明治四十五年における北海道の能楽 | 舟山 直治 | |
| ・事務局だより・編集後記 | ||
| 表紙レイアウト | 亀谷 隆 | |
| 第8号 | 1995.8 | |
 |
・表紙写真にちなんで シミコーン・ナジエーンの切り絵 | 中村 斎 |
| ・巻頭言 服部四郎先生の思い出 早稲田大学教授 菊池 徹夫 | ||
| ・事業報告 常務理事 柏倉 勝雄 | ||
| ・特集 サハリン・沿海州・カムチャツカの文化誌 | ||
| ・北サハリン・アレタサンドロフスタ土城について | 杉浦 重信 | |
| ・近年発見のサハリンの遺跡と遣物 セルゲイ・Ⅴ・ゴルフノフ | ||
| ・イワノフカ遺跡の動物形土製品 セルゲイ・Ⅴ・ゴルフノフ | ||
| ◎カラーページ さまざまな博物館交流の軌跡 | ||
| ・プガチェヴォ再訪 | 野村 崇 | |
| ・ワイデ山メドヴエーヂェフ洞窟 | 畑 宏明 | |
| ・南サハリン西海岸の旅 | 平川 善祥 | |
| ・ウラジオストック再訪 | 舟山 広治 | |
| ・カムチャツカ博物館見学記 | 金盛 典夫 | |
| ・博物館ノート 北方の白樺樹皮容器 | 福岡イト子 | |
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第7号 | 1994.9 | |
 |
・表紙写真にちなんで 蝦夷絵寸記 | 岡村吉右衛門 |
| ・巻頭言 研究交流と本の交換 北海道大学教授 菊池 俊彦 | ||
| ・事業報告一九九三年・九四年度の交流事業 常務理事 拍倉 勝雄 | ||
| ・特集Ⅰ 北方民族の詩展 | ||
| 「北方民族の詩」展を終えて | 舟山 廣治 | |
| ・シミョーン・ナジエーンの生涯と作品 | 中村 斎 | |
| ・蝦夷絵研究事始め-岡村吉右衛門先生に聞く- | 難波 琢雄 | |
| ・カラーページ | ||
| 「北方民族の詩」展 | ||
| 93~94さまぎまな北方博物館交流の軌跡 | ||
| サハリン中郡ワイダ山遺跡群を探る | ||
| シベリアの少数民族 チユーネル・M・タクサミ | ||
| 生きつづけるニプフの伝統文化 | 岡田 淳子 | |
| ワイダ山遺跡群踏査記 | 野村 崇 | |
| ・特集Ⅱ カムチャツカ・クリルの自然と文化 | ||
| カムチャツカ半島のヒグマ | 門崎 允昭 | |
| ベルグマンのカムチャツカ調査 | 杉浦 重信 | |
| 國後紀行 | 舟山 廣治 | |
| ・博物館ノート 北京故宮博物院の 「蕨手刀」 | 越田賢一郎 | |
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第6号 | 1992.12-北海道北方博物館交流協会会誌 | |
 |
・表紙写真にちなんで | 野村 崇 |
| ・巻頭言 北千島での懐い出から 会 長 渡邊左武郎 | ||
| ・事業報告 一九九一年度の交流事業 常務理事 柏倉 勝雄 | ||
| ・サハリン州文書館を尋ねて | 佐藤 京子 | |
| ・特集1 講演会「沿海州と日本の文化交流」 | ||
| 沿海州と中国・日本の文化交流 マルガリータ・A・パトルシエイヴァ | ||
| 環日本海地域と沿海州の交流について ナターリア・N・クズメンコ | ||
| パクローフカ文化(九~十三世紀)について ユーリイ・M・ワシーリエフ | ||
| 沿海州の金時代ガラデイシエ(山城、都城)の調査について | 天野 哲也 | |
| ・カラーページ | ||
| ・特集2 サハリンの史跡と文化を探る訪問団 | ||
| サハリン州博物館の旅 | 舟山 広治 | |
| 北サハリン考古・民族学紀行 | 野村 崇 | |
| 北方文化への開眼-故石附喜三男君への便り- | 鈴木 重治 | |
| ロシア極東地方の道路事情について | 小池 省三 | |
| ・新生ロシアの博物館再訪 | ||
| モスクワ、サンクト・ペテルブルグを訪ねて-ロシアにおける最近の博物館事情- | 舟山 広治 | |
| ロシア心象風景 | 斎藤 勝彦 | |
| ・博物館ノート | ||
| ピウスツキ国際シンポinサハリン | 中村 斎 | |
| 地方博物館の交流活動 | 村田 良介 | |
| ・事務局だより ・ 編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第5号 | 1991.11 | |
 |
●表紙写真にちなんで 「アリアドナ」 A・チエーホフ | |
| ●巻頭言 サハリンとの研究交流をとおして 静修短期大学教授 北川 芳男 | ||
| ●高倉新一郎先生の死を悼む 理事長 舟山 廣治 | ||
| ●秋の譜 十一月の悲歌 | 澤井 陽子 | |
| ●事業報告 一九九〇年度の交流事業 常務理事 柏倉 勝雄 | ||
| ●ウラジオ訪問の旅 -特集1 | ||
| ウラジオストーク紀行 理事長 舟山 廣治 | ||
| 沿海地方考古の旅 理 事 野村 崇 | ||
| ハバロフスク紀行 | 笹木 義友 | |
| ●カラーページ | ||
| ウラジオストック | ||
| ソ連科学アカデミー極東支部・博物館訪問'90.5 | ||
| 古画にみるアイヌ文化展・国際文学研究会議'90.9 | ||
| ハバロフスク文化局長・郷土博物館代表団の来道'91・9 | ||
| ●古画にみるアイヌ文化展 -特集2 | ||
| アイヌ絵と錦絵 弥永北海道歴史館館長 弥永 芳子 | ||
| 古画にみるアイヌ文化展に寄せて | 舟山 広治 | |
| 展示会「見知らぬアイヌ達」 ゴンドラトワ・タチアナ・アレキサンドロヴナ | ||
| ●博物館ノート | ||
| サハリンの自然 | 門崎 允昭 | |
| 日ソ共同両生・爬虫類調査を企画して | 佐藤 孝則 | |
| ●事務局だより | ||
| ●編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第4号 | 1990.10 | |
 |
表紙写真にちなんで 彌永北海道歴史館長 禰永 芳子 | |
| ・巻頭のことば 北を掘る 早稲田大学教授 櫻井 清彦 | ||
| ・事業報告 一九八九年度の交流事業 常務理事 柏倉 勝雄 | ||
| =特 集= | ||
| アントン・チエーホフ展を終えて 理事長 舟山 廣治 | ||
| ロシアの憂愁アントン・チエーホフ展シノプシス | ||
| チエーホフの「犬」をめぐつて 札幌市芸術の森美術館長 工藤 欣禰 | ||
| チエーホフにとってのサハリン旅行 大文学部助教授 灰谷 慶三 | ||
| 余韻を曳いて-あれから一年 | 澤井 陽子 | |
| カラーページ | ||
| 文化交流の大事業「アントン・チエーホフ展」公開に取組む | ||
| 交流の軌跡一九八九年 | ||
| アントンチエーホフ展回想 | ||
| 先住民族国際フェスティバル'89 | ||
| サハリン日ソ共同発掘調査おわる | ||
| ●'89北方民族国際フェスティバルから -白老一 理 事 中村 齊 | ||
| =報告特集= | ||
| 一九八九年サハリンにおける日ソ共同発掘調査報告 調査団長 野村 崇 | ||
| プロムイスロヴォエⅡ遺跡の発掘調査 富良野市郷土舘 杉浦 重信 | ||
| 一九八九年 サハリンの旅 斜里知床博物館長 金森 典夫 | ||
| サハリン州郷土誌博物館を訪ねて 帯広百年記念館 北沢 実 | ||
| ●篇集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 第3号 | 1989.7 | |
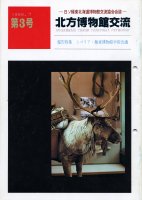 |
・メッセージ 北海道の皆さんヘ エルミタージユ美術館長 ポリース・ペトロフスキー | |
| ・事業報告 一九八八年度の交流事業常務 理 事 柏倉 勝雄 | ||
| ・報告特集 | ||
| ★極東博物館学術会議に参加して 団 長 中村 齊 | ||
| ★シベリア・極東博物館学術会議報告 副団長 野村 崇 | ||
| ★サハリン博物館研究者との交流 網走市立郷土博物館長 立脇 信雄 | ||
| ★サハリンヘ 利尻町立博物館 西谷 栄治 | ||
| ★南サハリンの遺跡を訪ねて 市立名寄図書館郷土資料室 氏江 敏文 | ||
| ★ナイバ河溯行調査 | 上田 秋男 | |
| ★ニブヒ民族の都ノーグリキを訪ねて (財)白老民族文化伝承保存財団 文化伝承課長 山丸 和幸 | ||
| ・カラーページ | ||
| ★博物館とベレストロイカ ロシア共和国文化省博物館局長 V・S・エフスチグネーフ | ||
| ★シベリアと極東開発の史的体験総括における博物館の役割 | ||
| ソ連科学アカデミー歴史・考古学研究所ウラル支部長 Ⅴ・Ⅴ・アレクセーエフ | ||
| ★極東開発史緊要の諸問題 ソ連科学アカデミー歴史研究所主幹研究員 A・I・アレクセーエフ | ||
| ★シベリア諸民族の文化研究における博物館の役割 | ||
| ソ連科学アカデミー人種誌学研究所 レニングラード支部シベリア極 東人種誌学部長 C・M・タクサミ | ||
| ・博物飴ノート | ||
| ヴァヴィーロフとその博物館 | 舟山 廣治 | |
| メンデレーフ博物館のこと | 紺谷 憲夫 | |
| 回想のチエーホフ | 工藤 欣彌 | |
| 南サハリンから擦文土器を発見 | 野村 崇 | |
| 編集後記 | ||
| 第2号 | 1988.3 | |
 |
巻頭のことば 副会長 渡邊左武郎 | |
| ・事業報告一九八七年度の交流事業 常務理事 柏倉 勝雄 | ||
| ・博物館代表団ソ連邦訪問報告 理 事 中村 齊 | ||
| ’=特 集= | ||
| 博物館交流を省みて 理事長 舟山 広治 | ||
| 文化・博物館友好交流報告 ノボシビルスク友好交流分科会 団 長 北川 芳男 | ||
| ・カラーグラビアー交流の記録- | ||
| 確かな交流の足跡 | ||
| 第3回極東・北海道友好交流会議 博物館交流~写真展公開 | ||
| シベリア・極東博物館視察団の交流一九八七年八月 | ||
| ソビエト連邦極東少数民族 -サハリンアイヌを中心として- | ||
| ・北海道博物館協会-シベリア・極東博物館視察団報告 | ||
| シベリア・極東の博物館を訪ねて 団 長 野村 崇 | ||
| 北海道と同じヒグマの住むシベリアの地を旅して 団 員 前田莱穂子 | ||
| ・博物館ノート | ||
| サハリン州郷土偉物館所蔵のアイヌコレクション サハリン州郷土博物館研究員 オリガー・A・シユービナ | ||
| ソ連におけるアイヌ民族研究の歴史 ソ連科学享T・レニングラ支部学術書記 アレキサンドル・B・スペワコフスキー | ||
| 編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |
| 創刊号 | 1986,12-日ソ極東北海道博物館交流協会会誌 | |
 |
創刊のことば 会長 高倉新一郎 |
|
| 日ソ極東北海道博物館交流のめざすもの 理事長 舟山 廣治 | ||
| 博物館交流事業の経過 常務理事 柏倉 勝雄 | ||
| =特 集= | ||
| ソ連極東博物館代表団を迎えて | ||
| 道民の皆さんへのメッセージ ソビエト社会主義共和国連邦文科省博物館局課長 リリアンナ・A・ドンスキフ | ||
| シベリア極東の博物館の諸問題 ロシア共和国博物館局長 ウラジミール・C・エフスチグニュフ | ||
| ハバロフスク地方郷土博物館の足跡 ハバロフスク地方郷土博物館長 エフレモフ・P・エフィモビッチ | ||
| カラーページ | ||
| 随 想 | ||
| ソビエト代表団の北海道訪問 各地の交流 | ||
| 北方民族博物館設立への期待 網走市長 安藤哲郎 | ||
| わがまちの日ソ交流 虻田町長 岡村 正吉 | ||
| サハリンへの途 白老アイヌ民族博物館長 山丸 武雄 | ||
| 博物館ノート | ||
| クレムリンの芸術的特徴 その建築・民芸絵画について モスクワ国立東洋民族芸術館研究員タチアナ・E・シェストワ | ||
| サハリン州立博物館にのこる旧樺太博物館時代の人類学等関係文献 北海道開拓記念館主任学芸員 紺谷憲夫 | ||
| 編集後記 | ||
| 表紙デザイン | 亀谷 隆 | |